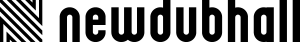パンク、そしてダブ
ダブ、という音楽、もしくは言葉を意識したというのはいつが最初なんでしょうか?
藤原まずは1978年ですね。それはやはりパンクがとにかく好きになったところからはじまりました。パンクのアーティストのインタヴューを読むと「ロンドンの、パンクのクラブではドン・レッツがダブをかけている」みたいなことがよく出てきたんですよ。そこから「ダブ」という言葉を意識しだして…… そのあと、たしか1979年か1980年だと思うんですけど、今野雄二さんが出ていたテレビ番組でも「ダブ」が紹介されていたのも見ました。それも印象に残っています。あとレコードとして買ったのは、マイキー・ドレッドとか、レヴォリューショナリーズとか、あとはリー・ペリーの『スーパー・エイプ』かな。そういったダブ・アルバムが当時、日本盤として出ていたんですよね。そういったLPを買ったのが最初ですね。
当時の場合、メディアの伝搬の仕方としては、言葉で知って、音は後から聴く感じだと思うんですけど。
藤原エコーとかリバーブの、あの「ウワンワンワン」という感じはテレビ・ドラマとかの、記憶喪失のときの効果音というか(笑)。いわゆるジャズとか、もともとのインストの音楽はともかく、当時は音楽というと歌があって当たり前という感じだったと思うんですけど、そんな時代にダブ処理してある音というのは新鮮で、どこか魅力的でしたね。その後はもうニューウェイヴの流れで〈ラフ・トレード〉とか、いわゆるポストパンク、あとはニュー・エイジ・ステッパースとかヴィヴィアン・ゴールドマンなんかを追いかけてましたね。
パンクありきっていういことですよね。
藤原パンクありきでダブを知るというところでしたね。
1980年代に入ると、そこからさらにクラブ・ミュージック的なもの、例えばヒップホップもあれば、後半になってくるとハウスもあってで。その部分でダブというのは、藤原さんのなかでずっとやはりあったものなんでしょうか。
藤原わりと当時の12インチはそこも地続きという感じで。B面にはダブというか、基本的にはインストが入っていて、常にそこにディレイ~リバーブ感というのがあるような感覚で。余談ですけど、そういえば当時、ハウスやヒップホップになると一気に日本盤が出なくなるんですよね、それまでパンクの頃とかは〈ラフ・トレード〉の7インチとかも結構ちゃんと日本盤で出てたのに。話しは戻りますけど、自分が東京に出てきた頃、まだ自分でDJをやる少し前なんですけど、当時はプラスチックス~メロンなんかを観つつ、原宿の〈クロコダイル〉で何度も観たのがルード・フラワー(こだま和文らが在籍したミュート・ビートの前身的バンド)。彼らはスカ、レゲエをやっていてすごくかっこよかったですね。ミュートになるとさらにもっとダブっぽくなりすますし。当時、そこにトシちゃん(故・中西俊夫)が出てたりしてたんで、それで一緒に行ったりとかね。リアルタイムで観ていたという意味ではルード・フラワー~ミュート・ビートですね。
なるほど。藤原さんのなかで、当時の印象的なダブの作品というと何になるんでしょうか?
藤原すごい好きだったのはやっぱりニュー・エイジ・ステッパーズかな。いまでもわりと聴きますね。ただ、エイドリアン・シャーウッドの仕事は〈On-U〉がスタートして以降、わりと音が硬質になっていって自分の好みではなくなっていくんだけど。ニュー・エイジ・ステッパーズのヘタうまヴォーカル的なところとか、ああいう感覚というのがすごい好きでしたね。

メジャー・フォース
とダブの関係
1980年代が中頃になると、ご自身のDJや高木完さんとのタイニー・パンクス / 〈メジャー・フォース〉で、ヒップホップの時代がくるかと思うんですけど、こうDJのときにそこにダブっぽいものが混ざってくるということはありました?
藤原正直思っ切りレゲエのものはないけど、わりと当時の12インチって、ディスコ・クラシックのB面に入っていたインストとか、リバーブのダブ感があったりとか、そういうものはかけてましたね。
1980年代も末に差し掛かると、DJとしての藤原さんはヒップホップから、むしろハウス・ミュージックの要素がどんどん強くなってくる時期だと思います。〈メジャー・フォース〉からは、長年にわたってハウス・シーンでクラシックとなっているT.P.O.名義の「Hiroshi's Dub」がリリースされるんですが。そこからいわゆるソロやさまざまなリミックス、それこそスチャダラパーの「N.I.C.E. GUY (NICE GUITAR DUB)」とか象徴的ですけど、ダブをひとつのテーマというか手法的に使われている印象があって。
藤原ダブってね、免罪符的なところがある気がするんですよね(笑)。ダブと言ってしまったら、DJ的な手法で作ったような音楽でも、一歩、音楽的にアカデミックに上がれるというか(笑)。とにかく、ディレイ、リバーブ感が好きなんですよね。でも、ディスコ・クラシックやハウスのB面とかもダブ・ヴァージョンが入ってますけど、それはやっぱりそういうリバーブ感っていうのに惹かれている人がすごいいるということなんだと思いますね。もちろん、僕もそこに惹かれましたね。
いわゆるヒップホップ的なブレイクビーツ、ダウンテンポにダブの要素というのは、その後の藤原さんもそうですが、そして同じく〈メジャー・フォース〉でいうと、もちろんミュートでも活躍されていた屋敷豪太さんがいて、そしてK.U.D.O.さんが手がけられたプロジェクトなどにもそうした要素があったりします。当時、ダンス・ミュージック・レーベル / クルーとしての〈メジャー・フォース〉のなかで、やはりダブというのは共通言語としてあったんでしょうか? もちろん、故・朝本浩文さん、宮崎泉(Dub MasterX)さんといったミュート・ビート人脈、さらにヤン富田さんがいたりと、周辺人脈のなかからダブという音楽性は切っても切り離せないものだとは思いますが。
藤原やっぱりK.U.D.O.と豪太がすごい好きで詳しかったというのはあったよね。(高木)完ちゃんとかトシちゃん(故・中西俊夫)はコアにラップというものが好きで、〈メジャー・フォース〉での音楽的なダブっぽさはやっぱりK.U.D.O.と豪太。僕もあのふたりからダブのレコードとか、いろいろダブのことについて教えてもらったりしたから。ヤンさんにももちろんいろいろ教えてもらいましたね。ヤンさんは僕にやっぱりすごい優等生という感覚があるんですよね。もうね、先生みたいな感じ。やっていることも、どこかピシッとちゃんとしているというか。アカデミックさが、僕らみたいな、「いい加減さ」というか、不良っぽさではもなくて、前衛的なところとか…… 本当に優等生なんですよ。何にでもくわしいので、さまざまな要素のなかのひとつとしてダブのことを教えてくれたりとか。

1990年代に入ると、本格的にソロ・アーティスト、プロデューサー、そしてリミキサーとして活動が本格化するわけですが。ソロもそうですが、例えばポップスのリミックスにしてもダブ感があったりとか、もちろんせいこうさんとのサブリミナル・カームとかも含めて、ひとつダブというのがサウンドのアイデンティみたいな感じで表出してきますよね。
藤原そういう音が自分のなかでスタンダードになっていたんでしょうね。当時、すごいロンドンが好きだったんで、それこそ小泉(今日子)さんもロンドン・レコーディングで豪太にやってもらったりとか。ロンドンの土地柄、やっぱりダブが染み付いている、その感覚が好きだったんだと思います。もう現地のエンジニアも、ほっとくとリヴァーブかけすぎというか(笑)。
なるほど、ご自身でもちろん好きだったいうのもあると思うのですが、K.U.D.O.さんとか豪太さん、あとは宮崎さんなどなど、そういった感覚の音源を実現できるアーティストが身近におられたというのも大きそうですね。
藤原そうですね。宮崎くんはやっぱりミュート・ビートの頃からずっとやって、ダブが好きですしね。
あとはロンドン経由のダブというのが大きそうですね。
藤原そうですね。まずはヒップホップが好きになって、ヒップホップが好きになった人はやっぱりアメリカ、ニューヨークに傾倒していく感じだと思うんですよね。でもニューヨークに行くと、やっぱりダブっぽさみたいなものはサウンドから薄れてしまう。対してロンドンに行くとヒップホップにもダブの感覚が入ってくるんですよね。ビーツ・インターナショナルなんかはまさにそうで。ソウル2ソウルもどっかダブっぽさはあるじゃないですか。あとはそこにラヴァーズ・ロック・レゲエみたいなものが入ってきたり。その部分で、ロンドン系か本当のヒップホップのアメリカ系かで分かれていたところはあると思う。そのなかで当時、僕はロンドンの方が好きだったんですね。
その後の1990年代前半から中頃というのは、ロンドンやブリストルあたりを中心にダビーな質感のブレイクビーツというのが出てきた時期で、藤原さんのソロはそことも同時多発的な感覚があったんじゃないかと。
藤原同時期にみんながああいう音楽を好きになった時代で、日本ではその手の音が遅れて出てきたわけでなく、UKと同じ頃にスタートできたということなんじゃないですかね。〈メジャー・フォース〉はとくに。