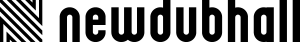はじまり
まずサウンド・エンジニアという仕事以前に、内田さんの音楽のルーツを。自分で買い集めたりとか能動的に音楽を聴くようになったのはなにがきっかけだったんでしょうか?
内田やっぱりラフィン・ノーズですね。中学の頃、『宝島』がいわゆる全盛期の時代で、自分は埼玉出身なんですが住んでいる街の本屋さんに2冊だけ『宝島』が入っていたんですよ。その1冊を毎月買ってとにかくすみからすみまで全部読んでいて、そこで知って。それ以前はテレビの歌番組で歌謡曲に触れたりとか、アニメの主題歌とか、そういうのはもちろん普通にあったんですけど、自分からのめり込んだのはやっぱりラフィン・ノーズ、そこからのパンクが最初ですね。パンクは音楽だけではなくそのカルチャー、ファッションやイデオロギー的なコトも含めてはまって。自分は埼玉の工業地帯で生まれ育ったんですけど、その境遇に非常にパンクがマッチしたんですよね。当時通っていたのがほとんどがヤンキーしかいない中学校で、僕自体はヤンキーじゃなくてむちゃくちゃカツアゲにおびえる毎日でしたね(笑)。僕にとって、そういうおびえるだけの毎日のはけ口となる、そんなカタルシスをパンクに求めていたというか。
具体的に音という点ではどこが一番ひっかかったんでしょうか?
内田やっぱりあのディストーション・ギターを聴くと頭が「シュワ、シュワ」となるというか。ギブソンのハムバッカーの音を聴くともう、ヤラれちゃったんですね。時代的には80年代で、すでにセックス・ピストルズはいないし、シド・ヴィシャスも死んでた時代ですけど。ラフィン・ノーズにはじまって、パンクも追ってました。でも同時にリアルタイムの音楽としてはスラッシュ・メタルが来てたんですよ。当時、ものすごく好きで、古いパンクとか、スラッシュ・メタル、両方聴いていて。
ラフィン・ノーズを起点に、過去と現在というか。
内田そういうことですね。
サウンド・エンジニアとしての直接の端緒としては、高校を卒業されて音響の専門学校へということのようですが、そのあたり、例えば当時に明確に好きな音楽と結びついていたり、すでに職業としてあこがれがあってそこを目指していたとかあるんでしょうか?
内田いや、それほど明確な目標があったわけではないんですよね。当時の仲の良い友だちが行くから、なんとなく決めてしまったという程度で。
楽器ではなくエンジニアというところで、子供の頃から例えば機械的なものが好きだったとか……そういうのはありませんでしたか?
内田思い返せば親父がカラオケ好きで家にぼろいカラオケ用の機材がいっぱいあったんですよね。テープ・レコーダーとか、父親が自分の歌声にかけたいだけで買ってきたエコーとか。たしかにそういうのを子供のときからいじるのは好きだったけど。そういえば、うちの父親は歌のないカラオケ・トラックばっかり家で聴いてて。
あ、レゲエで言うところの「ヴァージョン」じゃないですか(笑)。
内田この前も正月に帰ったときもカラオケばっかり聴いてるんだよ。もちろん、これはあまり関係ないけどさ(笑)。とはいえ、明確に将来の目標としてそういうのがつながっていたという感じはなくて、ただ、本当にぼ~っと考えてただけで。仲の良い友だちと「俺もそれに行くわ」ぐらいの感じですよ。サウンド・エンジニアという職業の認識も、高校の文化祭でバンドやって、音を出す機材をオペレートしているそういう職業の人が来てるな……ぐらいの認識ですね。
いわゆるサウンド・エンジニアといったときに、レコーディングのスタジオ・エンジニアとライヴPAのエンジニアと分かれると思うんですけど、専門学校とかもコースとか課程が違うんですよね?
内田そう、分かれるんですよ。1年は基礎的なところで、2年になったらどっちかのコースに自分の身の振りを考えないといけないんですよ。自分はレコーディングの方ですね。
ぼんやりとした目的から明確にレコーディングのエンジニアを選んだきっかけはなにが?
内田1年生のわりと早い時期、専門学校に通う乗り換えが高田馬場で、そこでオーパス・ワンというレコード店によく行っていて。そこはレゲエを扱っていて。それ以前、高校の時も音楽的な好奇心は結構ある方で、当時の80年代後半の空気のなかで、わりとパンク以外もスカとかサイコ・ビリーとかも聴いてはいたんですが、そのお店でダブに出会ってしまって。その音に衝撃を食らいました。その後、「しかもこれはエンジニアがやっている音楽なんだ」というのがわかって、そこから「そういえば、俺エンジニアの学校行ってるんだよな、コレがやりたい!」という衝動が走ったんですよ。


ダブ・エンジニアへ
当時衝撃を受けたダブ・アルバムは具体的にどのあたりなんでしょうか?
内田サイエンティスト『Scientist Wins The World Cup』。衝撃……というかその音の感覚としては、むしろ怖かった、背筋がゾッとしたというか、気味が悪いというのが正しいかも。若いときの耳って新鮮じゃないですか、その感覚でおっかないというか。しかもまだまだジャマイカからの輸入盤が少ない時期で、情報にしてもすごい少ない時代で、ダブってなんだろうってさっぱりわからなくて。あとレゲエにしてもボブ・マーリーすら聴いてない時期だったんだけど。
レコード屋にいって気になったという感じですかね。
内田簡単に言うとそうですね。やっぱりあのアルバムは、イラストのジャケットの引きも強いし。ともかく、そこからダブばっかり掘るようになってしまって。リアルタイムの音楽としては〈ON-U〉もインダストリアルの方で活動していた時期で。
ゲイリー・クレイルとかタックヘッドとか。
内田そうそう、そういう時期だったのでそういう音にもはまってしまって。そして自分が二十歳の時に、ちょうどリー・ペリーの初来日公演があったんですよ。バック・バンドはダブ・シンジケートとエイドリアン・シャーウッドでという。そのライヴにも衝撃受けて、とにかく「この音がやりたい」と思って。でも、おそらく楽器をやろうと思う人もそういう衝動ですよね。演奏や音源を聴いて「コレがやってみたい!」というのがやっぱりはじめにあると思う。
それが内田さんのなかではダブ・エンジニアだったという。
内田そうですね。Mute Beatの存在も大きかったですよね。Mute Beat自体は、ダブという音楽を意識する前からその存在は知っていて。当時例えば中学生の時代は航空会社のCMにも当時使われてて、テレビなんかにも出てたんで。だからMute Beat自体はすごい好きだったんだけど、ダブって感覚でMute Beatを聴いてなかったかもしれない。でも後から考えて、宮崎さん(Dub Master X)がエンジニアとしてメンバーにいるというのはスタンスとして画期的なことだったから。
そこから学校の2年時のコースの分岐でレコーディング・エンジニアのコースを選ぶわけですよね。そこから学校で学びつつ、就職活動みたいなことってするんですか?
内田専門学校2年時に企業研修というのがありまして、自分は新宿にあった〈テイク・ワン〉というスタジオに送られたんですね。そこのスタジオは、その後、お世話になる〈Olive Disk & Records〉の高橋(弘雄)さんが出入りしていて、Silent Poetsや竹村延和さんのSpritual Vibesなんかを手がけていて。クラブ・ミュージックというか、当時はアシッド・ジャズのブームが世界的にあって、その流れの日本版という感覚のアーティストですよね。そう言うものを〈テイク・ワン〉というスタジオでレコーディングしていたので、自分としてはここに入りたいと思って、バイトで入れてくださいという感じでアシスタントで入って。当時は、アシスタントといっても、スタジオなんてもろに体育会系の感じでしたから基本的に雑用というか。
大変そうですね……。
内田いわゆるエンジニア的なアシスタントもなにも、機材すら触れず馬券買いに行かされるとか(笑)。そこは1年いたんですが、自分が使い物にならなくてクビに。〈テイク・ワン〉自体は、吉野金次さん(注1)がその昔に作ったスタジオで、当時、吉野さんが作ったスタジオが3つか4つ都内にあって、そのなかのひとつに広尾に〈キャッツ〉というスタジオがあって、そこに俺を拾ってくれたエンジニアの人がいたんですよ。でもそこも3ヶ月でクビに。その後、佐藤(晴彦)さんが拾ってくださって、それで紹介されたのがチャゲ & 飛鳥の事務所が持っていたスタジオで(BURNISH STONE RECORDING STUDIO)。2回もクビになったんだけど、エンジニア自体はやめる気は全くなかったからお願いしますって言って、そこに入れてもらったんですよ。 注1 : レコーディング・エンジニア。細野晴臣や矢野顕子など、YMO周辺人脈のアーティストなどにも信認の厚かったレコーディング・エンジニア。
3度目の正直に。
内田やっとそこでアシスタント・エンジニアとしてどうにかできるようになって、やっと芽が出たというか。チャゲアスからも指名が来るようになって。もちろん、そういうスタジオなんで基本的には、ほとんどチャゲアスの仕事。たまにアイドルの仕事もありつつ、CMの仕事があったりで……自分的にはやっとアシスタントになれたんだけど、ちょっとモヤモヤしていた時期でしたね。そんなときにまた声を掛けていただいたエンジニアの方がいて。話は前後しますが、広尾の〈キャッツ〉時代に、ソウル・フラワー・ユニオンがレコーディングに来たことがあって。前身のバンド含めて彼らの大ファンだったので、当時かぶりつきで仕事をしてたんですね。で、そのレコーディングのエンジニアをやっていたのが加納直樹さん。俺のことをなぜか覚えていてくれたみたいで、「〈GO-GO KING RECORDERS〉(以下、ゴーゴーキング)というフル・アナログのスタジオを作るから一緒に来て手伝ってくれないか?」って誘われて。もう当時、チャゲアスのスタジオの社員になろうかと思っていた時期で、しかも「給料はチャゲアスのスタジオの半分になるけど」という。でも「そんなの全然行きますよ!」って、〈ゴーゴーキング〉にアシスタント・エンジニアとして入るという。