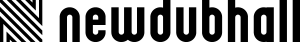New Culture Days
今回は〈Newdubhall〉のページでのインタヴューになるので、今度出る10インチ「New Culture Days」に関しての話題を中心にと思っています。この作品は近年のTHE DUB STATION BANDや、いわゆる客演ものと違った感覚の作品ではないかと思っています。もちろん、通底するこだまさんの音というのはバンドにしろ、こうした感覚のものも両方あるんですが、本作により近いという感覚で言えば、こだまさんが1990年代後半~2000年代初頭にご自身がトラックを作っていたソロの作品の延長線にある音に近いのかなと。今日はそのあたりの過去の話も含めてお聴きしたいと思っています。今回〈Newdubhall〉からオファーを受けて、デモ・トラックを渡されてというところからはじまっていると思いますが、まず聴いてどう思いましたか?
こだまとにかく「あまりにも音がないな」ということだよね。でも、こういうことを新たにやろうとしている、踏み出している若い人がいるんだなと思いましたよ。案外こういうことに踏み込んでいる人たちはいなかったからね。ダブにしても、実は結局、音数が多かったり…… ニュールーツとか、ステッパーになったり。いわゆる「迫力のある音」というのがずっと強かったからさ。そこでエフェクトも多くなっていくから…… だからダブの表現でこうした静かなほうというのはなかなかいないんだよね。
では、デモを聴いた段階で興味を持たれたという。
こだまもちろん。自分も音をなくしていって、自分が目指すなにか──静かなダブというかさ──でもそれはアンビエントではなくてね、ビートを感じさせるなにかという表現を自分でもずっとやってきたわけだからね。すぐに自分も理解できましたよ。でも、なにせキープしているリズムがないっていう。ここに僕がどうアプローチするのかというのは、しばらく考えましたよ。
Undefined側的に言えば、こだまさんにお願いしたのは?
サハラレゲエはとても懐の深い音楽だと思うんです。自分たちにとって、音響的な、空気が振動する感覚とか、アンプのノイズが聞こえる感じとか、それもレゲエの魅力、音楽性のひとつとして考えていて。そういった興味を音として表現するために作った曲ですね。できたときは、これがもはや正しい音楽なのかとか、それすらよくわからなかったんです。これにアプローチできるのは、こだまさんしかいないんじゃないかなって。
こだまだからね、この曲、言ってみれば乱暴な音でしたよ。レゲエというと、レンジが大きいので誤解されるんだけど、逆に今回のような音が理解されないというか。僕が『Requiem DUB』をやった頃──全部自分の打ち込みでやった時代──それからいろいろ表現していて感じてたことだけど、レゲエとか、ソウルとか、こうした音楽の基本として“ダンス”というのがひとつ要素として強いわけだ。それは絶対的なダンス・ミュージックと言ってもいい。その要素を裏切るというのは、なかなか勇気がいることだよね。「踊れないじゃん」というひとことで、「これは困ったな」となってしまう。でも、それをあえて飛び越えるということなんだよね。しかもこの作品は、アンビエントでもなく、アヴァンギャルドなものでもなく、限られたところを突き詰めていくものという感覚はあった。彼らの音は今回はじめて聴いたんです。つまり突然僕のところにやってきたんですよ。でも、すぐに納得できるところがあった。
面識はあったんですよね。
こだまありましたよ。
サハラでも、あったはあったんですけど、The Heavymannersをやっているときに挨拶させてもらったりぐらいで。DRY&HEAVYのサポートをやってるときは、ちょうどこだまさんがライヴにご病気で出れなくなったりというタイミングで。だから、本当に自分からの一方的な挨拶ぐらいでした。
こだまそうか、そうか。

めくるめく日々
エレクトロニック・ダブというか、本作のサウンド的な感覚にベーシック・チャンネル~リズム&サウンド以降のミニマル・ダブというのは間違い無く延長線上にあると言えると思います。そしてこだまさんの作品には前述のように、まさに同時代にミニマル・ダブ的なサウンドを展開されていた、と僕は解釈しています。そこで質問なんですが、そうしたサウンドとの出会いみたいなところでこだまさんに聴きたいんですけど。おそらくなんですが、これは遡ると、1980年代の〈ワッキーズ〉との出会い、さらにその後の1990年代のベーシック・チャンネル勢がやっていた〈ワッキーズ〉の再発を通じて、ミニマル・ダブの音楽と出会うというのがひとつあるのかと思いますかどうでしょうか?
こだまそう、最初にリズム&サウンドの音源を聴いたというところでいうと、「Mango Walk」の再発12インチですね(注1)。これもやっぱり不思議な、そして幸せな巡り合わせというか縁があってね。〈ワッキーズ〉はいま言ったように1980年代から一緒にやったりというのがあるんだよね(注2)。〈オーバーヒート〉やレゲエ・ジャパン・スプラッシュを、当時〈ワッキーズ〉のプロデュースなんかをやっていたソニー落合が仕切ってたこととか。まず、はじめにマックス・ロメオのバックバンドとして、〈ワッキーズ〉のリズム・フォースが来日して、そこにホーン・セクションで僕が入ったのが1985年とか。それはオーバーヒートの石井が無茶振りでね、ホーン隊がいないからっていう……その前はマイティ・ダイアモンズもあるんだけど。とにかく、そんななかでロイド・バーンズと知り合って。でもそれよりも前から僕自身は、1980年代に入って、ボブ・マーリーなんかもやっとちゃんとまともに聴くようになったころに〈ワッキーズ〉は作品として出会っていたんだ。あるときニューウェイヴのコーナーに〈ワッキーズ〉のアルバムが入っていてね。1980年頃、それは自分にとってレゲエとニューウェイヴのコーナーを両方見るような時代だったんだよね。その頃に〈ワッキーズ〉を知るわけですよ。その頃、絵を描いている友人がいて、その彼が「NYのおもしろいレゲエがあるんだよね」って言って教えてもらったのがきっかけだと思うんだけど。その後、まさか自分が20代の頃にたまたまそうやって聴くことになった〈ワッキーズ〉と、後々、そこのアーティストと一緒に演奏したり、代表者でもあるロイド・バーンズと関わり合いを持つとは思ってなかったわけ。
注1:1998年に〈リズム&サウンド〉からリリースされたThe Chosen Brothers / Bullwackies All Stars「Mango Walk」とリズム&サウンドによるリメイク「Mango Drive」のスプリット盤。
注2:1988年のMute Beat『Dub Wise』にもロイド・バーンズは参加している。
まさに縁ですね。
こだまそういう巡り合わせもあってね。しかもリズム&サウンドの話までいくと、そのマーク・エルネストゥス(注3)。彼はベルリンでレコード屋(〈ハードワックス〉)をやっていて、そこでNY〈ワッキーズ〉の作品を扱っていたんだよね。 注3:リズム&サウンドはマークとモーリッツ・フォン・オズワルドによるユニット。

自分もですが、ある世代にとっては彼らが再発をしたことで〈ワッキーズ〉のサウンドを知った人が多いと思います。
こだまその後、リズム&サウンドは日本にもよく来る時代が来て、共演するということもあったわけだよ。実は、また僕がリズム&サウンドと出会ったときにキーマンがここで出て来るんだよね。さっき「〈ワッキーズ〉いいよ」って僕に教えてくれた絵描きの彼がまたキーマンなんだけど。1980年代初頭に〈ワッキーズ〉をすすめられてから10年ぐらいして、今度は「これいいよ」って進めてくれたのがリズム&サウンドだったんだよね。さっきも言ったけど、最初に手にしたリズム&サウンドの作品は「Mango Drive」という曲。(元ロッキンタイムのベース、小粥テツンド君からのバースデープレゼントだったと思う。)でもその片面は〈ワッキーズ〉の再発で「Mango Walk」──つまりは〈ワッキーズ〉のロゴのラベルがついたレコードというわけ。逆サイドだけど、片面は〈ワッキーズ〉のロゴのレコードだから、リズム&サウンドの方を聴いたとき「ロイドすげえのやりはじめたな」って思ったんだよ(笑)。
なるほど(笑)。
こだますごいインパクトだよね。「ロイド、ここにきたか!」と思ったんだけど、その後、すぐにリズム&サウンドっていうユニットがやっている音だってわかって、「そうか」と思ったよね。
リズム&サウンドを聴いたときに、どこにひかれました?
こだまちょっとね、正直言うとやりたかったことを先にやられてしまった感はあったよね。自分がレゲエやダブをずっと聴いてきて、楽曲も作ってきて、いよいよ「自分が今後やるのはこんなサウンドだ」って思っていた音があったんだよ。しかも全部自分の打ち込みで、ちょうどその頃、100パーセント自分が作ったサウンドで曲が作れるという体制にやっとなっていて。そうすると自分の「絵」を書きやすいよね。その先にあったもの、自分で見出したい音、それを先に見せられてしまった感じはあるよね。
なるほど。
こだましかも当時、ベース、低音の表現というものに魅力を感じていたというか、苦しんでいたわけだ。日本だとジャマイカの音を聴いても、「なんでこんな低音のベースが出るんだろう」という悩みは、1980年代から当時1990年代も続いていた問題だと思うんですよ。それをさらにすごい形でリズム&サウンドは出してきたんだよね。もちろん、他のヨーロッパのアーティストたちとかもいたと思うけど、例えばマッド・プロフェッサーとかスミス&マイティとかも、デジタルでベースを表現することはあったと思うけど。ものすごいハイとローのレンジを広げた音をみんな見出したというか。でもリズム&サウンドの音はね、それにしてもティキマンのアルバムなんかを聴いても「これがドイツ、ベルリンなのかな」と感心したんだよね。

とはいえ、同時代性という意味ではこだまさんの作品もそこまで大きく出遅れていたわけではないんですよね。むしろ今回調べてびっくりして。リズム&サウンドことベーシック・チャンネルのふたりが、そのエレクトロニック・ダブ路線へとフォーカスした〈Burial Mix〉をリリースしたのが1996年。といってもまだミステリアスでアンダーグラウンド、日本においてはテクノにおいてもまだそこまで注目されていなかった時期だと思います。そして、転機となった「Mango Walk」が1998年のリリース、これがリズム&サウンドのレーベルとして2番なんですが、こだまさんのエレクトロニック・ダブな作品としては、1999年の『Requiem DUB』、2000年には『Stars』とその後「Nazo」や「A Silnet Prayer」と続きます。そしてある意味でリズム&サウンドへの回答とも言えそうな2001年のKTU(こだま和文+TICO+内田直之)がリリースされています。そこまでタイムラグがないことを考えれば、やはりこだまさんがお一人で作られていたものと、偶然にも見ている方向が一緒だった。しかもその先に〈ワッキーズ〉のサウンドがひとつその原点にあるという共通項もありつつ、という感じだったのではないかと。
こだま同時進行だったんだろうね。それが妙な縁なんだと思うんだよね。説明しにくいけどさ。その手前でリー・ペリーと出会えたこととか。(オーガスタス)パブロと一緒に共演できたこととか、ある種、1985年代から2000年のその頃まではとても大事なそういう出会いがあった時期なんですよ。そこにはフィッシュマンズが入ってきたりしてね。本当にめくるめく日々だったんですよ。
ジャマイカやNY、ベルリン、日本と、世界の音楽を巡る点と点で結ばれるという。
こだまそう目まぐるしくね。この縁の話は世界が大きくなりすぎちゃうんだけどね。